圧力容器の主な部材について2
圧力容器の主な部材について、前回は耐圧部材について解説しました。今回は非耐圧部材のうち、外部部品について解説します。非耐圧部材とはその名の通り、圧力がかからない部分です。圧力容器の外側に付くものは外部部品(エクスターナル)、内部に付くものを内部部品(インターナル)と呼ぶこともあります。外部部品の代表的なものとして、サポートラグ、サポートレグ、スカート、サドル、リフティングラグ、テーリングラグ、トラニオン、銘板座、アースラグ、強め輪、保温サポート、プラットフォーム、ラダーなどがあります。外部部品には圧力はかかりませんが、強度を検討する必要があるものが多々あります。またその形状や溶接の仕方などについても規格で細かく決められているものもありますので、設計するにあたってはそれらについて把握しておく必要があります。
圧力容器を支持する部品
圧力容器はコンクリートの基礎の上に置いたり、鉄鋼構造物上に設置されることが一般的です。圧力容器やその中の流体などの重量を支持するだけの強度が最低限必要になります。また、地震がある地域に設置するものは耐震性を、屋外に設置するものは風荷重に対しても耐えられるように設計する必要があります。圧力容器の支持形状の種類としては以下のようなものがあります。
たて型の圧力容器の円筒胴部に設けられます。4点で支持するのが一般的ですが、小型な圧力容器では3点や2点で支持するものもあります。セットボルトで固定し鉄鋼構造物上などに設置します。
たて型の圧力容器に使用されます。レグは脚のことでその名の通り、脚のように圧力容器をサポートします。比較的小型な圧力容器でよく用いられます。脚の本数は4本が一般的ですが3本で支持するものもあります。鉄鋼構造物上にセットボルトで固定したり、コンクリート上にアンカーボルトで固定したりされます。
スカートたて型の圧力容器に使用され、下部の鏡板部に円筒状の胴部を設け、接地面にベースプレートやベースブロックを設けた構造です。スカートの内部にアクセスするためのマンホール、通気用のベントホール、その他ノズル貫通用のノズルオープニングが設けられます。
サドル
横型の圧力容器に使用され、円筒胴部の下側120°以上の部分に設けられます。数は通常2点です。両方がガッチリと固定されると温度変化による熱膨張、収縮によって固定点に応力が発生する可能性があります。そのために一方を固定とし、もう一方のボルト穴を長孔として可動とすることで応力の発生を抑えます。また、コンクリート上に設ける場合は可動側にスライディングプレートを設けて伸び縮みに対応できるようにします。
圧力容器を吊り上げる時に用いる部材
圧力容器は製作工場から据付場所まで運ぶ際に、つり上げて輸送車両などに載せる必要があります。また、たて型の容器の場合は(小型なものを除いて)横倒しにして運ぶことがほとんどです。機器をつり上げたり、ハンドリングするためのラグが設けられます。これらの機器は現地に据え付けた後は不要となることが多いので、据え付けた後に切断してしまうこともあります。
リフティングラグ圧力容器をつり上げるためのラグです。通常、容器の上部に設けられ、リフティングラグで上部を、テーリングラグで下部を吊り上げて使用します。リフティングラグには吊り上げ時の機器の荷重が作用するため、吊り上げ時の荷重を考慮した強度を持たせた設計が必要になります。リフティングラグは板の水平方向には強いですが、板厚の方向の荷重には弱いため、吊り上げる際の角度に注意が必要です。どうしても適切な角度で吊り上げることができない場合は、吊り天秤を用いて垂直に吊り上げるようにします。
テーリングラグ
圧力容器の下部に設けられ、リフティングラグとともに用いて機器を横倒しにするなどのハンドリングに用います。リフティングラグと同様、吊り上げ時の荷重に耐える強度を持つように設計が必要です。
トラニオン
リフティングラグと同様に圧力容器を吊り上げるためのものですが、下図のような円筒状の形状をしています。比較的大型な機器や重量が大きい機器などで用いられます。トラニオン自体の強度検討はもちろんのこと、吊り上げ時の荷重でシェルが歪んでしまわないかも考慮するのが適切です。
その他の外部部品
プラットフォームは圧力容器の外面に設けられる足場で、圧力容器の点検やメンテナンスを行う際に、作業員が安全にアクセスできるようにするためのものです。ラダーははしごのことです。上部に人がのって作業をしても大丈夫なように強度を確保する必要がありますが、JPIにおいてある程度寸法が規定されているので、こちらを参照されると便利です。(写真はフリー素材から拝借しました)
銘板座
機器の銘板を取り付けるための座です。銘板は据付後に見やすい位置に設けましょう。また保温を被せる機器は保温に埋もれてしまわないように機器表面から保温の厚さを考慮して距離を取るようにしましょう。また、銘板に記載すべき事項についても法規で定められていますので、ちゃんと記載しましょう。アースラグ
アースラグはアース(接地)を取るためのラグです。通常機器の下の方などアースが取りやすい位置に設けられます。アースを取ることで、静電気の帯電を防止し災害の発生を防ぎます。強め輪
外圧が作用する圧力容器の内部または外部に輪状に設けられ、圧力容器の剛性を高めるためのものです。外圧に対する強度を計算する場合の支持ポイントになります。強め輪自体も十分な剛性を持っていなければなりませんので、設計にあたっては検討する必要があります。
保温サポート
圧力容器には外部に保温を設けるものがあります。その保温材をサポートするためのものです。
まとめ
今回は圧力容器の非耐圧部材のうち、外部部品について解説しました。直接圧力を保持するところでは無いものの、設計にあたっては適切な強度を持っていることを確認する必要があります。各規格でもいろいろと規定されておりますがそれらを全て覚えておく必要はありません(都度規格を確認すればよいので)。何が定められてるのか、何を検討しないといけないのかを押さえておきましょう。










![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/332fd766.5fdb6cca.332fd767.cd5554b4/?me_id=1213310&item_id=17460326&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4233%2F9784526074233.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/332fd766.5fdb6cca.332fd767.cd5554b4/?me_id=1213310&item_id=19036655&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4338%2F9784542304338.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


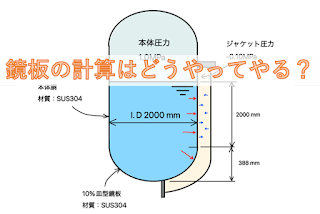
コメント
コメントを投稿