溶接継手効率とは?
今回は溶接継手効率について説明したいと思います。細かな内容ですが、胴や鏡板の必要板厚を求めるのに必須な情報になります。適切な溶接継手効率の選び方について、理解していただけると思いますので、是非お読みください。 溶接の形状による分類 溶接継手効率の説明に入る前に、圧力容器の溶接にはどのようなものがあるのかを、簡単に説明します。圧力容器の溶接には様々な形状がありますが、最も重要な溶接といえる溶接は、 長手溶接 と 周溶接 でしょう。 Fig.1 溶接継手の位置による分類 長手溶接 とは、以下のFig.1のように円筒胴の断面に対して垂直な方向に行った溶接のことです。一方の 周溶接 は円筒胴の断面方向に対して行った溶接のことです。長手溶接線のことをL線、周溶接線のことをC線などと呼ぶことがあります。また、鏡板が複数の板からなる場合の継ぎ目の溶接線は、長手溶接線の扱いになります。 圧力容器の溶接はその溶接の場所によって分類がなされています。Fig.1はJIS B 8265の図3の抜粋です。A〜Eの5つの分類に分けられていることがわかります。溶接継手効率が関係するのは耐圧部の溶接のみであり、分類A〜Dが対象となります。 ではそれぞれどのような箇所に用いられるのかを見ていきましょう。それぞれの分類は、ざっくりと以下の通りです。 分類A すべての長手溶接継手 球形胴、鏡板、平鏡板、ふた板の溶接継手 全半球型鏡板と円筒胴の、円すい胴、管台等の溶接継手 分類B すべての周溶接継手(ただし全半球鏡板と円筒胴、円すい胴、管台等の溶接は除く) 分類C フランジと管台、円筒胴および円すい胴等の溶接継手 分類D 管台と円筒胴、円すい胴、鏡板等の溶接継手 分類E 強め輪、支持(スカート、サドル、レグ、ラグ等)および耐圧部材に直接溶接する非耐圧部材の溶接部 溶接継手効率とは? そもそも溶接継手効率とは何でしょうか。先に述べた通り、溶接と一口に言っても色々な形状があります。また、溶接に欠陥がないかを調べる 放射線透過試験 を実施するか...


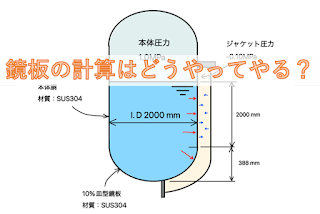
コメント
コメントを投稿