日本国内における圧力容器の法規・規格とは?
圧力容器は内部に圧力によるエネルギーを蓄えているため、万が一破裂が生じた場合は周囲に大きな被害を及ぼしかねません。
そうした事故を未然に防ぐために、規格や法規が制定されています。
ではどのような規格や法規があるのか、それがどのような場合に適用されるのかを知っておくことは圧力容器の設計者として一丁目一番地といえるでしょう。
規格とは?法規とは?
法規と規格の違いから説明します。
まず規格とは何でしょうか?
「規格」とは製品や材料など「基準を定めたもの」です。
圧力容器の設計に関してはJIS B 8265やJIS B 8267などに記されております。
また多管式熱交換器についてはJIS B 8249、フランジについてはJIS B
2220など、特定の項目については別途規格が設けられています。そのほかにも検査に関する規格や材料の規格も設計するうえで適宜参照する必要があります。
日本の法規は基本的にJIS B 8265に沿った内容となっています。初めての方はとりあえずはJIS B
8265を理解するところから始めたらいいのではないかと、個人的には思います。
また、ほかにも日本石油学会が発行する規格のJPIというものもあります。
JPIは独自にフランジの基準や、レグ・ラグサポートの基準、プラットホームの基準などを定めています。意外と参考にすることが多いです。
ただしこれらの規格自体には強制力がありません。
例えば、ある圧力容器が「JIS B 8265に基づいて設計すること」となっていたとしても、JISの協会に届け出るわけでもないので、第三者が監査して指摘するわけでもありません。
一方で「法規」とは読んで字のごとく「法律で定められた規則」のことであり、法的な強制力が伴います。したがって、圧力容器の設計にあたっては、適用される法規の内容に沿って、設計・製造・検査が行われなければなりません。
日本での圧力容器に関係する法規は、高圧ガス保安法、労働安全衛生法、電気事業法、ガス事業法などがあります。
これら4つの法律は圧力容器関連4法と呼ばれております。
高圧ガス保安法
高圧ガスによる災害を防止するために、高圧ガスの取り扱い(製造・貯蔵・販売・移動・輸入消費・廃棄)やボンベや貯槽などの容器の製造・取り扱いを規制する法律です。
経済産業省の所管であり、検査及び合格証の発行は高圧ガス保安協会(KHK)が行います。
では「高圧ガス」とはどのような定義なのでしょうか。
同法によると高圧ガスの定義は以下の通りです。以下のいずれかに該当するものが「高圧ガス」となります。
また高圧ガスの製造設備のうち、災害の発生を防止するため設計の検査、材料の品質の検査、製造中の検査を行うことが必要なものを「特定設備」といいます。
特定設備に該当するのは以下の条件以外のものです。
・設計圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が0.004以下の容器。
・内容積が0.001m3以下であって、設計圧力が30MPa未満の容器。
そのほかにも適用外となる条件があります。詳しくは経済産業省の以下のサイトをご参照下さい。
特定設備に該当する容器は「特定設備検査規則」に基づいて、設計・検査を行う必要があります。
労働安全衛生法
労働災害を防止するための法律であり、厚生労働省の所管になります。
その中の「圧力容器構造規格」において、圧力容器の設計や検査に関して規定がされております。
労働安全衛生法では「第一種圧力容器」「第二種圧力容器」「小型圧力容器」の3種の圧力容器は規定されています。
それぞれ以下のように適用区分が定められております。
まとめると第一種圧力容器は
「0.1MPaを超える、大気中における沸点を超える温度の液体を保有する容器」で、
第二種圧力容器は
「0.2MPa以上の気体を保有する容器」
であるといえます。
ただし、高圧ガス保安法の適用条件にも該当する場合、高圧ガス保安法が優先されます。
電気事業法
発電所に用いられる圧力容器に適用される法律。火力発電所と原子力発電所の圧力容器についてそれぞれ技術基準が設けられています。
高圧ガス保安法や労働安全衛生法が適用されるような圧力容器であっても、発電所に設置される場合は電気事業法が適用されることになります。
ガス事業法
ガスを供給する設備の圧力容器に適用される法律。都市ガスの製造工場の圧力容器(ガス発生装置やガスホルダー)などに適用されます。
消防法
消防法は火災を予防し、火災または地震による被害を小さくするための法律です。
危険物はその分類に応じて指定数量が定められています。
その指定数量の5分の1以上の量を貯蔵するタンクの場合、20号タンクに該当し、
消防法の規制の対象となります。
20号タンクは所轄消防署立会いのもと、水張り試験または水圧試験を実施する必要があります。
まとめ
圧力容器に関連する規格や法規を紹介しました。
これらすべてを熟知する必要はないと思いますが、自分の勤め先で必要となる法規の知識を少しずつ体得していけばよいと思います。
本ブログでは圧力容器の設計者にとって必須となる事項を今後も記事にまとめてまいりますので、ほかの記事も併せてご覧いただければと思います。
まとめ
日本国内の圧力容器に関する規格
- JIS B 8265 圧力容器の構造 - 一般事項 : 日本の法規はこの規格にほぼ準拠
- JIS B 8249 多管式熱交換機
- JIS B 2220 鋼製管フランジ など
日本国内の圧力容器に関する法規
- 高圧ガス保安法 特定設備検査規則 : 1MPa以上の圧縮ガスまたは0.2MPa以上のアセチレンガス・液化ガスを保有する容器などに適用
- 労働安全衛生法 圧力容器構造規格 : 0.1MPaを超える大気圧における沸点を超える温度の液体を保有する容器が第一種圧力容器に、0.2MPa以上の圧縮気体を保有する容器が第二種圧力容器に該当します。その他小型圧力容器の規定もあり。
- 電気事業法 : 発電所に用いられる圧力容器に適用される。
- ガス事業法 : ガス製造設備に用いられる圧力容器に適用される。
- 消防法 : 指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵する容器は20号タンクとなる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/332fd766.5fdb6cca.332fd767.cd5554b4/?me_id=1213310&item_id=17460326&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4233%2F9784526074233.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/332fd766.5fdb6cca.332fd767.cd5554b4/?me_id=1213310&item_id=19036655&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4338%2F9784542304338.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)


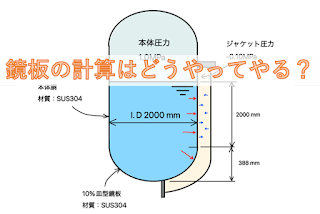
コメント
コメントを投稿